
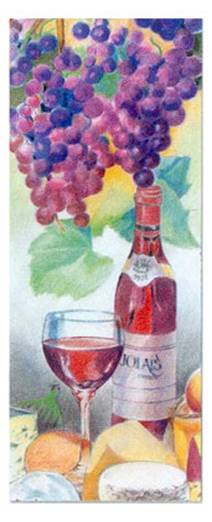
 「虎杖」(いたどり、スカンポ
「虎杖」(いたどり、スカンポ

NFジャーナルの表紙に戻る
Copyright (C) 2008 DAIKON_TOM(HTML化)
Modify 2008. Sep. 2 第1.0版
ブドウ療法の真髄: 「レズベラトロル」 1916年に、当時40歳だった南ア出身の(自然療法)女医ジョアナ・ブラントは、母親が癌で死んでからまもなく、 自分も胃癌にかかっていることを知った。そこで、食餌療法で何とか、癌を根治しようと色々試みた。 その結果、肉食は癌の増殖を促すが、菜食は癌の増殖を抑えることにまず気づいた。 さらに、特にどんな野菜や果物が癌の抑制に寄与するかを検討した結果、赤ブドウ療法が一番良いという結論を 9年間にわたる研究によって得た。 彼女は1928年に(南アから米国に移民して、「ハーモニー・センター」という食餌療法センターを設立後まもなく)、 「天然(化学肥料を使わないで)栽培した赤や紫色のブドウの絞り汁を毎日飲んで、自分の胃癌を根治した」という 体験を「(癌の)ブドウ療法」(The Grape Cure) というタイトルで、100ページほどの本にして出版した。 その後、彼女は40年以上、健康な生活を全うしたそうである。 http://www.arnoldehret.org/healthclub/grapecure.html それでは、この赤ブドウ汁の中にある抗癌作用を持つ物質は一体何だろうか? 以後70年以上の月日をかけて、 多くの学者によって、「ブドウ療法」の科学的根拠を探る研究がなされ、1997年になってようやく、 米国シカゴにあるイリノイ大学のジョン・ペズットのグループによって、その抗癌物質が「レズベラトロル」という ポリフェノールの一種(R3、水酸基を3つ持つスチルベン)であることを突き止めた。 癌の治療には、毎日15ー30 mg の「R3」服用が必要といわれている。 「R3」は、赤ブドウの主に果皮の部分に含まれている。従って、この果皮を使って作られる赤ワインには R3が豊富だが、(赤い果皮を使わない) 白ワインにはR3がほとんど含まれていない。 成年ならば、赤ワインを適度に飲めば、癌の予防や治療に役立つと考えられる。 さて、2002年に英国のライセスターにあるデュモンフォート大学のジェリーポッターのグループにより、 R3は癌細胞内に豊富にある酵素の働きによって、さらに水酸化されて、より制癌作用の強い「ピシアタノル」(R4) という誘導体に変化することがわかった。 正常細胞にはこの酵素が少ないので、R3は癌細胞の増殖を選択的に抑制することができる。 それでは、R4はいかなるメカニズムで、癌細胞の増殖を抑えるのだろうか? 1994年に米国ニューメキシコ大学のジャネット・オリバーのグループによって、 R4がチロシンキナーゼの一種である「SYK」を特異的に阻害することが明らかにされていた。 さらに1997年になって、米国ロチェスターにあるメイヨー病院のポール・リスボンのグループによって、 この「SYK」がPIー3 キナーゼの活性化に必要であることが発見された。 従って、R4は最終的にはPIー3 キナーゼの下流にあるキナーゼ、PAKやAKTなどの活性化を遮断することが、 2002年に米国のフロリダ州にあるリー・モフィット癌センターのジュリー・デュジューのグループによって、 実際に証明された。 さらに翌年、米国ラットガー大学のチー・タングとミネソタ大学のジガング・ドングの共同研究によって、 R4の誘導体である「MR5」が最も強い抗癌作用をRAS癌に対して発揮することを見つけた(IC50が約0。5 micro M)。 この合成誘導体は、スチルベン骨格の5つの水酸基が全部メチル化されたものである。 さらに面白いことには、R3/R4により抗癌フォスファターゼ「PTEN」の発現も促進されるらしいことが、 2005年に米国オハイオ州立大学のチャリス・エングの研究室によって明らかにされた。 言い換えれば、R3はどうやら「二刀流」で(SYK阻害とPTEN発現を介して)下流にあるPAKとAKTを共に遮断しているようである。 従って、理論的には「Bio 30」と同様、「MR5」(あるいは天然の赤ブドウ汁) がすいぞう癌やNF腫瘍などの 難病の治療に役立つ日が将来、到来することを期待してよかろう。 ついでながら、R3は癌に効くばかりではなく、アルツハイマー病(AD)、ハンチントン病(HD)、ルー・ゲーリック病(ALS)などの 神経変性疾患にも治療効果があるらしい。 例えば、2005年に米国のロングアイランド(ユダヤ)医科研のピーター・デービスのグループは、R3やその誘導体「TMS」 (スチルベン骨格の4つの水酸基が全てメチル化した、いわゆるMR4)がADの病因であるベータ・アミロイド (BA)ペプチドの 分解を促進することを報告している。 「ブドウ療法」と共に「断食療法」の併用を唱えるブラント女史のこのユニークな原書「The Grape Cure」が欧米で出版されて以来 既に80年にもなるが、不思議にも日本読者向けの邦訳が出版されたという形跡が全く見当たらない。 日本人には概して「食いしん坊」あるいは (絶滅に瀕する鯨の肉まで食べる)「美食家」が多いから、 断食や節食がうけないためなのだろうか? あるいはグレープジュースや赤ワインを飲む習慣が日本社会にはまだ広く普及していないためなのだろうか? もし邦訳に「なぜ赤ブドウや節食 (カロリー制限) が癌に効くか、長生きに寄与するか」という科学的な根拠を詳しく解説すれば、 この「一見素朴に見える」古典に信憑性が備わって、読者の関心を呼び起こす (引き寄せる) ことができるかもしれない。 長寿遺伝子とR3 豪州出身、ハーバード大学医学部病理学のデビッド・シンクレア教授 の研究室により、2003年になって、 なんとR3が酵母に存在する長寿遺伝子産物である「SIR2」という酵素を活性化することが明らかにされた。 この酵素はNAD依存性のHDACの一種であり、抗癌蛋白であるp53などの脱アセチル化に関与する。 p53のアセチル化は、その抗癌作用、例えば細胞増殖抑制作用 (や細胞死促進作用) を抑えるので、 SIR2あるいはそれを活性化するR3は、p53の活性化を介して、細胞増殖を抑え、酵母やショウジョウバエや 線虫「エレガンス」の寿命を延ばす働きをもつ。 さて、ヒトを含めて哺乳類にも、SIR2に相当する長寿遺伝子 (SIRT1)が存在することがわかっている。 SIRT1もR3やカロリー制限 (CR)によって活性化され、マウスなどの哺乳類の寿命を有意に延長する機能をもつことが 証明されている。 しかしながら、オランダの研究グループからの2004年の報告によれば、哺乳類では、SIRT1の主な標的は (アセチル化された) FOXO4という転写蛋白で、エレガンス中で長寿に関与している「Daf16」と呼ばれる蛋白に相当し、 R3によって、脱アセチル化されると、その転写機能が促進される。 ちなみに、FOXO4の転写機能は、アセチル化ばかりではなく、発癌性のAKTによる燐酸化によっても制御 (抑制) されていることが、同じオランダの研究グループによって、2002年に報告されている。 後述するが、発癌性のPAKも別の経路により、FOXO4の機能を抑制している。 言い換えれば、AKT/PAKを含めて発癌をもたらすシグナルは、種々の経路を介して、我々の寿命を短くすることに 寄与している。 前述したが、R3はキナーゼ 「SYK」を阻害することによって、最終的には (発癌性の) AKTおよびPAKを遮断するので、 結果的にはFOXO4を活性化し、寿命の延長に寄与することになる。 AMP キナーゼ (AMPK) の活性化 さて、「カロリー制限」(CR、節食あるいは絶食)に伴って、糖(グルコース)濃度が低下すると、細胞内のATPの濃度も低下し、 相対的にAMPの濃度 (AMP/ATP比) が高まる。そのような状態に細胞がおかれると活性化するキナーゼがある。 AMPキナーゼ (AMPK) がその典型的な例である。 面白いことには、このキナーゼの活性が高いと、寿命が長くなるという現象が知られている。 つまり、カロリーの低い食事 (腹八分目) をしていると、長生きするというわけである。その理由が2007年になってわかった。 米国のスタンフォード大学のアン・ブルネ (フランス出身)のグループによって、長寿/抗癌蛋白の一種 Daf16/FOXOがAMPKによって燐酸化され、かつ活性化されることが見つけられた。 従って、FOXOの抗癌/延命機能は、発癌性キナーゼ「AKT」により抑制され、抗癌キナーゼ「AMPK」により促進されることになる。 さらに同じ年に、米国のセントルイスにあるワシントン大学のジェフ・ミルブランドのグループは、絶食(あるいは節食)しなくても、 R3 (あるいは赤ブドウ汁) をせっせと摂取していれば、寿命を延ばすことができる証拠をもう1つ見つけた。 前年のマウス実験で、R3が何らかのメカニズムにより、AMPキナーゼ を活性化することを、シンクレアのグループが 見つけていた。さらに、このAMPK活性化には、抗癌キナーゼ「LKB1」による燐酸化を必要とするが、 (R3やCRによって活性化される) SIRT1を全く必要としないという意外な事実が、ミルブランドのグループにより発見された。 つまり、R3 による寿命の延長には、SIRT1を介するアセチル化経路やSYK/AKTを介する燐酸化経路のほかに、 LKB1とAMPKを介する第3の経路が関与していることが明らかになったわけだ。 従って、R3やグレープジュースを摂取すれば、いわば「一石三鳥」の恩恵がある(癌が治り、 ADなどの神経変性疾患にかかりにくくなり、そして何よりも健康で長生きできる) ことが期待される。 なお、商業的には(赤ブドウよりずっと安価な)日本原産の雑草「虎杖」(いたどり、コジョウ、スカンポ)のエキスが最近、 R3の主な原料になっているそうである。赤ブドウのうちで、R3含量が最高なのは、米国南東部原産の「マスカディン」と呼ばれる 赤黒い品種で、このブドウからできる「マスカディン」ワインには、リットル当たり、R3が14ー40 mgも含まれている。 http://hirotami.iza.ne.jp/blog/entry/132819 R3誘導体の大量醸造への夢 1988年以来、ドイツのフライブルグ大学のヨアキム・シュレーダーのグループなどによって、R3の生合成に関与する遺伝子が いくつかクローンされ始めた。 これらの遺伝子 (VST1やVST2など) を小麦に紫外線照射することによって人工的に発現誘導させ、 小麦をカビ耐性にすることが、2005年にハンブルグ大学のホルスト・ロルツの研究室によって成功した。 この技術を使えば将来、ムギはもちろん、虎杖などの雑草、あるいは大腸菌などのバクテリアからでも、R3やその誘導体を 大量生産することができる可能性が出てきた。実際、2007年になって、東京大学農学部の堀ノ内末治教授の研究室により、 大腸菌にR3合成酵素(RS)系を発現させて、R3の誘導体を合成することに成功したと聞いている。 従って、大腸菌を使って、R3誘導体の大量発酵 (醸造) を見る日はそう遠くはないだろう。 グレープジュースや赤ワインを適度に飲んで、健康的な新年を迎えよう! 文責: 丸田 浩 (薬学教授、豪州メルボルン永住) 問い合わせ: maruta19420@mac.com
「虎杖」(いたどり、スカンポ
Muscadine Grapes (R3含量が最高!)
NFジャーナルの表紙に戻る
Copyright (C) 2008 DAIKON_TOM(HTML化)Modify 2008. Sep. 2 第1.0版